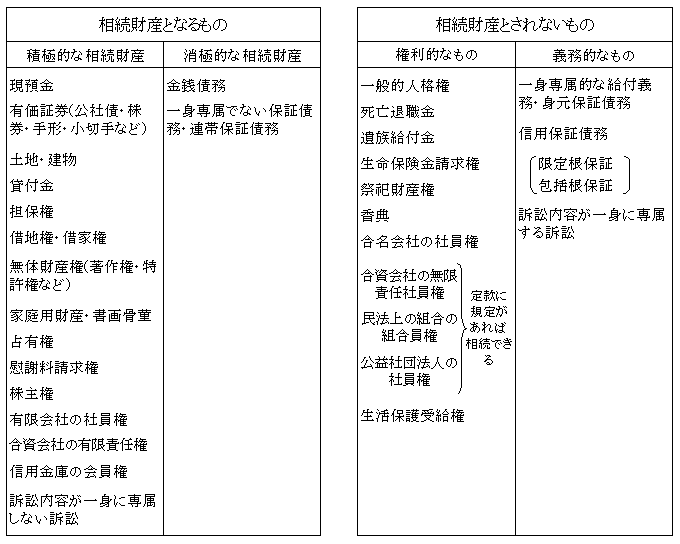
| 四.相続財産の概略把握 | |
| 被相続人が相続開始のときに有した積極財産および消極財産(債務)を包括して相続財産といいます。一般に財産法上の権利義務は相続財産として相続の対象となりますが、権利義務の性質、内容によって相続されないものがあります。 | |
| 1.相続できる財産 | |
|
現金・預金・社債・公債・株券・手形・小切手などの有価証券、土地・建物などの不動産、債権や債務など、被相続人の一身に専属するものを除き承継されます。留置権・先取特権・質権・抵当権のような担保権や借地権、借家権、また、著作権や特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの工業所有権も相続できることが認められています。 通常の保証債務および連帯保証債務も、身元保証など信頼関係を基礎にした一身専属的なものを除き相続されます。金銭債務のように分割できる債務は相続分に応じて分割承継されます。連帯保証債務も相続人らは被相続人の債務を分割承継し、各自その承継した範囲で本来の債務者と連携して負担します。 賃貸借契約での貸借人のための保証も相続性のある債務とされています。被相続人の生命が侵害されたことによる慰謝料請求権も被害者である被相続人が請求意思を表明したか否かに関係なく、当然に相続すると解されています。 | |
| 2.相続できない財産 | |
|
(1)一身専属的な権利義務 一身専属的な権利義務は被相続人の一身に専属して帰属し、その人だけが権利を享受し義務を履行し得るという性質のもので、権利者の死亡とともに消滅します。 例えば姓名権、教授契約により生ずる権利や被相続人の人格にのみ結びつけられた給料を内容とするもの、芸術家、著作家の給付義務、扶養の権利義務などです。身元保証債務や信用保証債務(根保証)も、保証人と被相続人との間の特別な信任関係を前提としますので、保証人の死亡によって消滅します。また保証人に一定の資格があることを前提とする保証債務も同様と解されています。 | |
|
(2)死亡退職金 死亡退職金については受給権者の範囲や順序が法令や労働契約、就業規則などで取り決められていることが多く、その取り決められている受給権者の固有の権利として一般に相続財産となりません。ただし、相続税計算上はみなし相続財産となり課税財産となります。 | |
|
(3)遺族給付金 遺族給付金として遺族に支給される金員は遺族の生活を保障しようとする生活扶助的要素を持ち、受給権者の固有の権利として一般に相続財産となりません。 | |
|
(4)生命保険金請求権 生命保険金請求権については、民法上、受取人を指定したときはそれらの人が固有の権利として取得し相続財産となりません。また受取人を被保険者の相続人と指定している場合も被相続人が死亡したときに相続人が固有の権利として取得し相続財産となりません。 ただし相続税計算上はみなし相続財産とされ課税財産となります。 | |
|
(5)系譜、祭具及び墳墓 系譜、祭具および墳墓の所有権は慣習に従い一般の相続財産とは異なった取扱いを受けており、祖先の祭祀を主宰する者が承継します。 | |
|
(6)香典 香典は死者の供養や遺族の悲しみを慰め、家族の負担を軽減するための贈与と考えられ、本来葬式費用の祭祀の費用に充当すべく祭祀の主宰者に与えられたものと考えられます。 | |
|
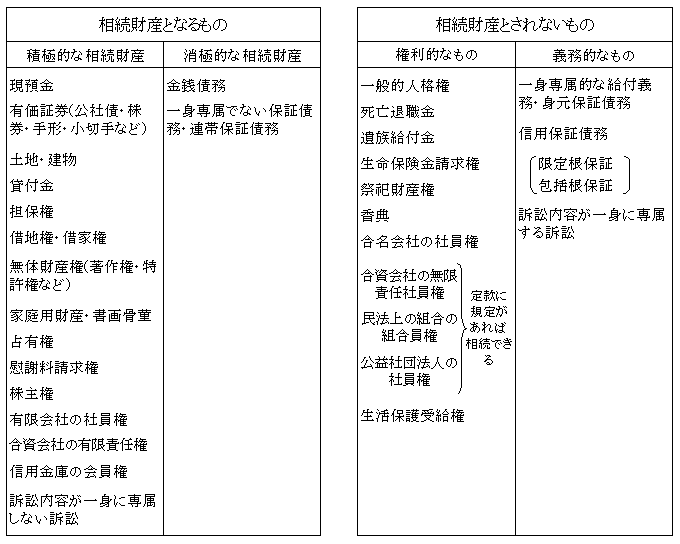
|
| 3.相続財産の把握 | |
|
(1)固定資産税納税通知書 固定資産税納税通知書は、各市町村が土地・建物を所有している人に対して毎年4月頃に送付しています。逆からいいますと固定資産税納税通知書を受けていた故人は、その市町村に土地または建物を所有していることになりますので、送付してきた市町村役場へ行き故人の土地および家屋の名寄帳を取得しますと、土地および建物の所有状況がわかります。 なお、土地または家屋の所有権はあるが、登記簿上名義の変更がなされていない場合には納税通知書は送付されませんので、故人と係り合いのある出生地などの不動産の状況がどうなっているか確かめる必要があります。 | |
|
(2)金融機関からの送付書類 金融機関から何らかの送付書類がある場合には、故人と取引関係があったことになりますので、その金融機関へ行き、故人が死亡した日の残高証明書(預金・株式など)を取得すれば相続財産が捜せます。 | |
|
(3)保険契約書 保管してある保険契約書の保険料支払書を確認し、故人が支払っていた保険契約があれば、それも相続財産になります。 | |
|
(4)契約書 金銭消費貸借契約書などにより債権債務などの相続財産がわかります。 | |
|
(5)確定申告書 過去の確定申告書の所得の状況により相続財産がわかります。 配当所得−株式 不動産所得−土地・建物 事業所得−事業用資産 | |
| 4.預金通帳の入出金の状況から捜す | |
|
(1)入金状況から捜す 次の入金の状況から相続財産がわかります。
| |
|
(2)出金状況から捜す 次の出金の状況から相続財産がわかります。
| |
| 5.人を頼りに捜す | |
|
(1)兄弟・親類 故人が連絡をとっていた兄弟・親類は、過去に故人が購入した財産や金銭の貸し借りなどの話しを聞いていることがあります。この人たちから故人の財産状況など知っていることを聞きだします。 | |
|
(2)友人 友人も兄弟や親類と同様に、故人が購入した財産や金銭の貸し借りなどの話しを聞いていることがあります。 | |
|
(3)顧問弁護士・会計士・税理士 故人の財産状況を一番よく知っているといえます。特に、顧問会計士や税理士は故人の事業にかかわる不動産・債権債務はよく知っているはずです。 | |
|
(4)会社の人事部 故人が会社に勤めていた場合には、死亡退職金や弔慰金、その他会社との債権債務などは、会社の人事部の人から説明を受ければ会社関係の相続財産はわかります。 |