法定相続人には、被相続人の配偶者(配偶者相続人)と被相続人の血族関係者で一定のもの(血族相続人)に限られています。
婚姻届がなされている配偶者は常に相続人となります。婚姻届がなされていない内縁の夫婦では、いくら長年連れ添っていても相続人にはなれません(民890)。
相続人になれる血族関係者とその順位は次のように定められています(民887,889)。
[1]第1順位…被相続人の子などの直系卑属
[2]第2順位…被相続人の父母、祖父母といった直系尊属
[3]第3順位…被相続人の兄弟姉妹
血族相続人は、まず第1順位の相続人から優先的に相続人となり、第1順位の相続人がいなければ、第2順位の血族関係者が相続人になり、第2順位の相続人がいないときは第3順位の血族関係者が相続人となります。そして第1順位から第3順位までの相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続することになります。
血族相続人のうち、被相続人の子および兄弟姉妹で、被相続人より先に死亡しているなど相続権を失っている場合には、その子供(孫または甥、姪)が、代わって相続人になることができます(次の[1]〜[3])。これを代襲相続人といいます。
[1]相続人となるべき者が被相続人の死亡前に死亡している場合
[2]相続人となるべき者が相続欠格者の場合
[3]相続人となるべき者が相続の廃除を受けたとき
なお、相続を放棄した者、配偶者、直系尊属には代襲相続は認められていません。
また、代襲相続人となるべき孫について[1]〜[3]の事由に該当し相続権を失ったときは、さらにその子(曾孫)まで代襲相続(再代襲相続)が認められています(民887)。
民法で定める法定相続分は次のようになっています(民900)。
| 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
| 第1順位 | 1/2 | 1/2 | − | − |
| 第2順位 | 2/3 | − | 1/3 | − |
| 第3順位 | 3/4 | − | − | 1/4 |
同順位の血族相続人が数人いるときの各人の相続分は原則として均等となります。例えば、相続人が配偶者と子供が2人のときは、子供の相続分は、それぞれ1/2×1/2=1/4となります。
[1]認知した子の相続分
認知した非嫡出子(内縁の妻との間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(正妻の子供) の相続分の2分の1となります。
なお、非嫡出子で認知されていなければ、相続権はありません。
[2]半血兄弟姉妹の相続分
父母の一方のみ同じくする半血兄弟姉妹の相続分は父母の両方を同じくする全血兄弟姉 妹の相続分の2分の1となります。
[1]相続の放棄があった場合には、その放棄をした者ははじめから相続人ではないものと みなされます。
[2]養子は法律上の実子とみなされますので、実子と同じ相続分を持つことになります。
|
被相続人と相続人の 戸籍謄本を取り寄せて調べます。 |
法定相続人の範囲と順位
欠格者とは次に掲げる人をいいます(民891)。
| [1] | 被相続人や自分より先順位で、あるいは自分と同順位で相続人となるべき者を故意に殺 しまたは殺そうとして刑罰を受けた者。 |
| [2] | 被相続人が殺されたことを知っていながら、その犯罪を告発または告訴しなかった者。 ただし、その者に事のよしあしを判断する能力がないとき、または犯人がその者の配偶 者や直系血族であったときは除かれます。 |
| [3] | 被相続人をだましたり強迫したりして、被相続人の遺言の行為、遺言の撤回または変更 を妨害した者。 |
| [4] | 被相続人をだましたり強迫したりして、遺言をさせたり、遺言の撤回または変更をさせ た者。 |
| [5] | 被相続人の遺言を偽造・変造・破壊または隠したりした者。 |
欠格者となった相続人は相続開始のときから欠格者として取扱われ、相続する権利を失うことになります。しかし、欠格者の子(直系卑属)の代襲相続権には影響を与えませんので、欠格者の子(直系卑属)が代襲して相続財産を取得することができます。
また、被相続人が欠格者に対して遺言により財産を遺贈することになっていたとしても欠格者は遺贈により財産を取得することができません。
被相続人を殺そうとして処罰されたり、先順位や同順位の相続人を殺したりまたは殺そうとして処罰された場合には、その相続人は欠格者となります。しかし、その後被相続人が自分の意思で欠格者となった相続人を許し欠格の取消しをした場合には、その欠格を許された相続人は相続財産を取得することができます。
廃除者とは、遺留分を有する相続人が被相続人に対して虐待をし、あるいは重大な侮辱を加えたとき、または相続人として目に余る非行をした場合のその相続人をいいます。
前述した(1)の行為をした遺留分を有する相続人がいる場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てるか、被相続人の遺言により遺言執行者が家庭裁判所に申立てることになります。
廃除者となった相続人は相続開始のときから廃除者として取扱われ、相続する権利を失うことになります。しかし、廃除者の子(直系卑属)の代襲相続権には影響を与えないので、廃除者の子(直系卑属)が代襲して相続財産を取得することができます。
また、被相続人が廃除者に対して遺言により財産を遺贈することになっている場合には、欠格者の場合と異なり、廃除者は遺贈財産を取得することができます。
| [1] | 未成年者…満20歳に達していない人 |
| [2] | 禁治産者…精神障害のために合理的な判断をすることができない人 |
| [3] | 準禁治産者…心身耗弱者および浪費者 |
親権者には未成年者の親がなります(民818)。図の場合には、法定相続人が被相続人の配偶者、孫A、孫B、子Cの4人となります。子Cの親権者は被相続人の配偶者となりますが、配偶者と子Cは双方とも相続権があるために遺産分割について双方とも権利主張ができる点で利益相反の関係にあります。また、孫Bの親権者は配偶者B´となり、孫Aには親権者がいないことになります。孫Bの相続手続は配偶者B´がすれば良いのですが、孫Aと子Cの相続手続は親(親権者)がすることはできません。
子Cの親権者は被相続人の配偶者なのですが、子Cも配偶者も被相続人の法定相続人となるため、両者は利益相反の関係にあり配偶者が子Cの相続手続をすることができません。この場合には親権者である被相続人の配偶者は、家庭裁判所に子Cの特別代理人の選出を請求しなければなりません。請求するときには特別代理人の候補者を選出しますが、通常親族を候補者として特別代理人の選出を請求しているようです。
家庭裁判所が選出した特別代理人は子Cの相続手続(相続の放棄や遺産分割など)をすることになります。
親権者いない場合において遺言で後見人の指定がないときは、親族または債権者等の利害関係人が家庭裁判所に対し後見人選出の申立てをすることになります(民841)。
家庭裁判所が選出した後見人は孫Aの相続手続をすることになります。また被相続人の遺言で後見人の指定がされているときは、その指定された後見人が孫Aの相続手続をすることになります。
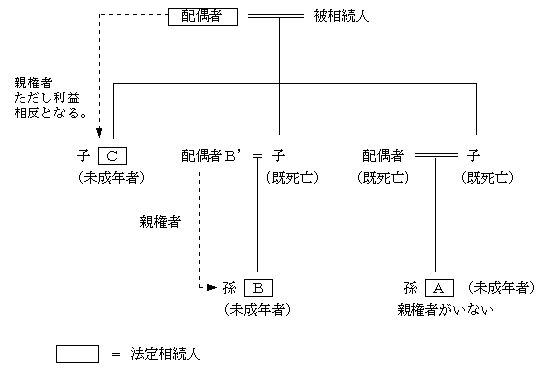
| (1) | 相続開始前に後見人が選任されている場合 → 選任されている後見人 |
| (2) | 遺言により後見人が指定されている場合 → 指定された後見人 |
| (3) | 禁治産者に配偶者がいる場合 → 配偶者(法定後見人) |
| (4) | 上記(1)〜(3)に該当する人がいない場合 → 家庭裁判所が選任した後見人 |
| (1) | 相続開始前に保佐人が選任されている場合 → 選任されている保佐人 |
| (2) | 遺言により保佐人が指定されている場合 → 指定された保佐人 |
| (3) | 準禁治産者に配偶者がいる場合 → 配偶者(法定保佐人) |
| (4) | 上記(1)〜(3)に該当する人がいない場合 → 家庭裁判所が選任した保佐人 |
| [1] | 未成年者 |
| [2] | 禁治産者および準禁治産者 |
| [3] | 家庭裁判所よりやめさせられた法定代理人、後見人、保佐人 |
| [4] | 破産者 |
| [5] | 未成年者、禁治産者、準禁治産者に対し訴訟をしていたり、またはしたことのある人、および、その者の配偶者が直系血族 |
| [6] | 行方不明者 |
相続人または包括受遺者のなかに未成年者がいるとき、ふつう代理人には親権者である親がなります。しかしその親も同時に相続人である場合、親は子どもの代理人にはなれません。子どもと代理人の間に利害関係ができてしまうからです。同じ理由から、ほかの相続人や包括受遺者も代理人になることはできません。
このようなときは、家庭裁判所にその子どもと利益が相反しない人を特別代理人に選任してもらいます。
| ■ | 申し立て書 「特別代理人選任申立書」。申し立て先にある |
| ■ | 申し立て人 親権者またはほかの相続人 |
| ■ | 申し立て先 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| ■ | 必要なもの [1]未成年者の戸籍謄本 [2]申し立て人の戸籍謄本 [3]特別代理人候補者の戸籍謄本 [4]特別代理人候補者の住民票 [5]申し立て人の印鑑 |